海外研究留学するのに、1番良い方法として、海外学振を獲得するのが、
もっとも
「成功」に近づきます。
そこで、今回は
海外学振の申請のポイントについて説明します。
海外学振を獲得するためのポイント
2. 海外で研究する意義がしっかりしていること
3. 申請書を他人に読んでもらい、客観的な意見を聞く
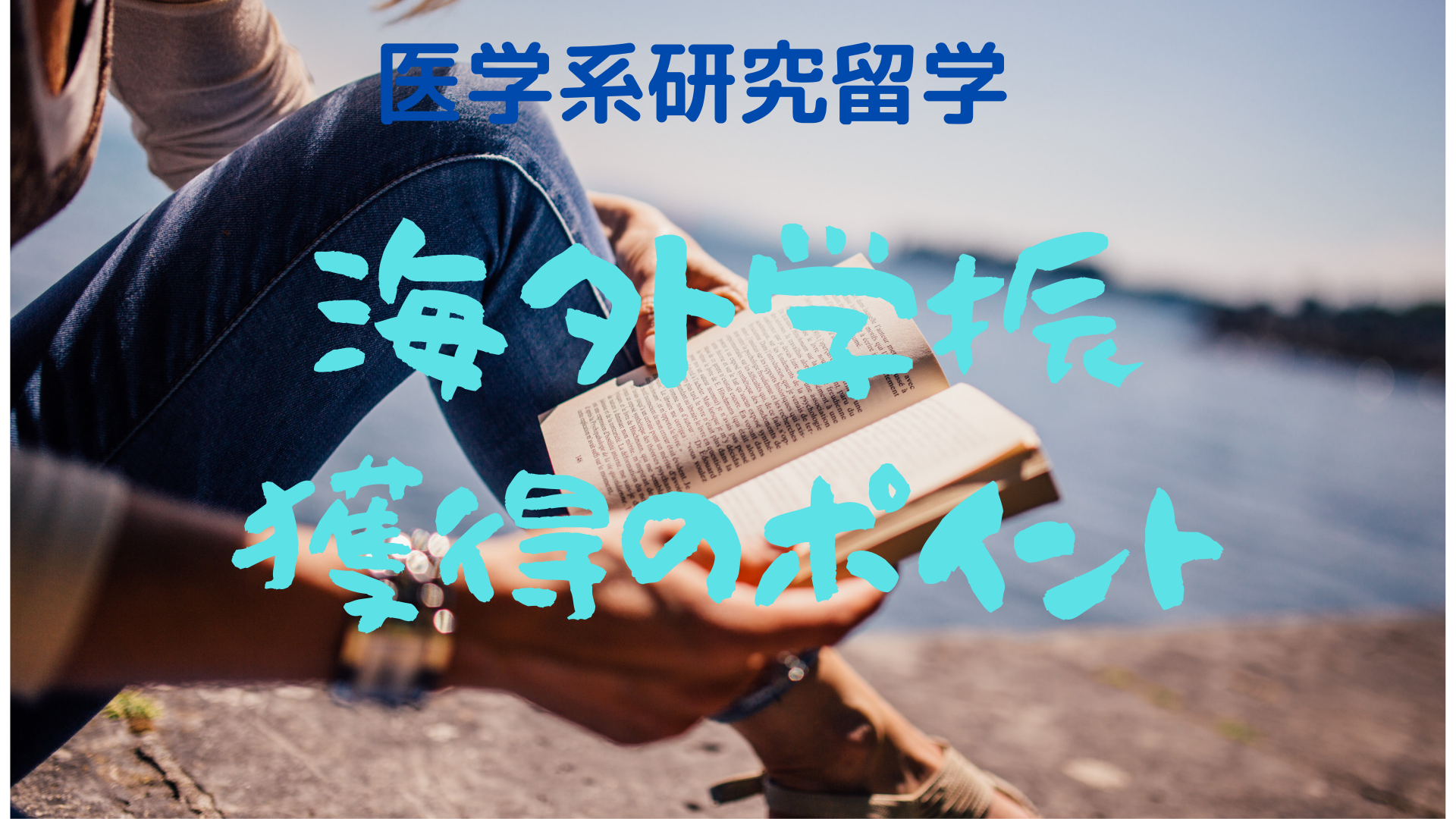
海外研究留学するのに、1番良い方法として、海外学振を獲得するのが、
もっとも
「成功」に近づきます。
そこで、今回は
海外学振の申請のポイントについて説明します。
海外学振を獲得するためのポイント

今まで
研究留学のススメ-0:研究留学のメリットとデメリット
研究留学のススメ-1: 研究留学を成功させるための心得
研究留学のススメ-2: 研究留学のための準備の仕方
を説明してきました。
今回は、研究留学先の選び方について説明していきたいと思います。
研究留学の準備の進め方の時に、
留学先の当てがない場合やコネクションがない場合の探し方として
助成金申請と同時に、縁もゆかりもない研究室のボスに「研究助成金を申請したいので、もし助成金を獲得できたら、あなたの研究室で働かせてください」メールをするといいですよっ
って書きました。
では、どのように縁のゆかりもない研究室を探せばいいのでしょうか?
方法は、大体下記の2つがあります。
あらかじめ書いておきますが、
この2つの方法は、成功率がかなり低いです。
ですので、コネクションがあれば、例えば、直属の上司の知り合いなどがあれば、
そこを研究留学先とするのが無難です。
私が研究留学先を探した際は、
なんのコネクションもありませんでした(笑)
もう手探りでいろいろ試しました。
私が実際、実践した方法として、
海外にポスター発表した際に、ポスターのところに、自分の名刺と、主要論文のコピーとを何十部とコピーしておいておきました。さらに研究留学先を探していますって書いておきました。
それで、私の研究発表ポスターを見に来てくれたり、興味を持ってくれた方に、拙い英語でアピールしました。
非常に恥ずかしい思いをしましたけど、10年経てばいい思い出です。
でも、ほとんど手応えなく、一箇所、面接まで行きましたが、結局断られました、、、
その面接のために、自費でアメリカまで行ったんですけどね、、、
2007年ぐらいの話ですけど。
今だったら、zoomとかskypeとかありますから、そんな手間は必要ないのでしょうけど。
メールもしまくりました。
自分の研究テーマに近いところを中心に。
何十通出したか分かりません。100通は行かないと思いますが、50は超えていたと思います、、、、
まあ、10出して、1つ返事があるかないかでした。
返事があっても、今はグラントがないから〜と、断りのメール。
まだ返事があるだけ、ましという感じでした。
結局、私の場合は、「研究留学ネット」の求人サイトから、運よく、面接を経て、採用されました。現在、研究留学ネットは2019年から更新されていませんね、、
コロナの影響だと思いますけど。
また更新されたら、ぜひ利用してみてください。
面接、面談について、
英語が得意ではないヒトは、「え〜!面接〜嫌だな〜」
って思われるかもしれませんが、
私も初めは、躊躇しました。
英語も得意ではなく、ザ ジャパニーズイングリッシュしか喋れませんでしたし、、(今でもですけど、まあ、その当時より多少マシにはなってますけど、、、)。
そこは、覚悟を決めてやりましょう!!
恥をかいても、多くの人とは二度と会いませんから。
大事なのは「気合と根性」です(笑)
さて、今はzoomとかで簡単に「面接」ができます。
それでも、一度は研究室に見学に行くことをお勧めします。
もしくは、その研究室の他のポスドクや、その施設に日本人ポスドクがいるなら、
論文や、大学等のホームページからメールアドレスを検索して、メールしてみましょう。
「あの研究室やボスがどんな感じですか?」って。
なぜかって?
別に海外の研究室を探す時だけではなく、
日本でもそうですけど、
職場の「空気感」を肌で感じることが大事です。
雰囲気がわるい研究室は、その部屋に入れば、雰囲気で伝わります。
もしくは、そこで働いているポスドクと話せば、ダイレクトにその研究室の雰囲気がわかります。
それができないなら、メールでもいいので、どういう研究室か探りを必ず入れましょう。
パワハラって日本だけではなく、アメリカでもどこでも、ありますからね!!
私がいた施設でも、ある日本人ポスドク(ベテランのお医者さん)が、安い給料で、馬車馬のように、もしくは奴隷のように働かされて、理不尽な要求ばかりされて、心が病んだという話を聞きました。
縁もゆかりもないからって、留学できたらどこでも良いって考えがちですが、
ブラック研究室は絶対、避けましょう!!
ブラックを避けるために、大事なこととして、
必ず給与(サラリー)について、最初から、面談の時から妥協しないでください。
最低限のサラリーは、決まってます。
いくら、研究留学がしたいからといって
給与が安くても良いとか、
タダでも良いとか、いってはダメです。
初めから足元見てくるようなボスは、100%「ブラック」です。
そんなところに、研究留学しても、ろくなことになりません!
気をつけてください。
ちなみに私のボスの場合、はじめから、規則通りのサラリーを提示してくれました。
何かと辛かったですけど、そういうボスの研究室だったからこそ、
頑張れたのだと思います。
以上。
海外研究室の選び方でした。
ぜひ、良い研究室に留学して、プライスレスな良い経験を手に入れてください。
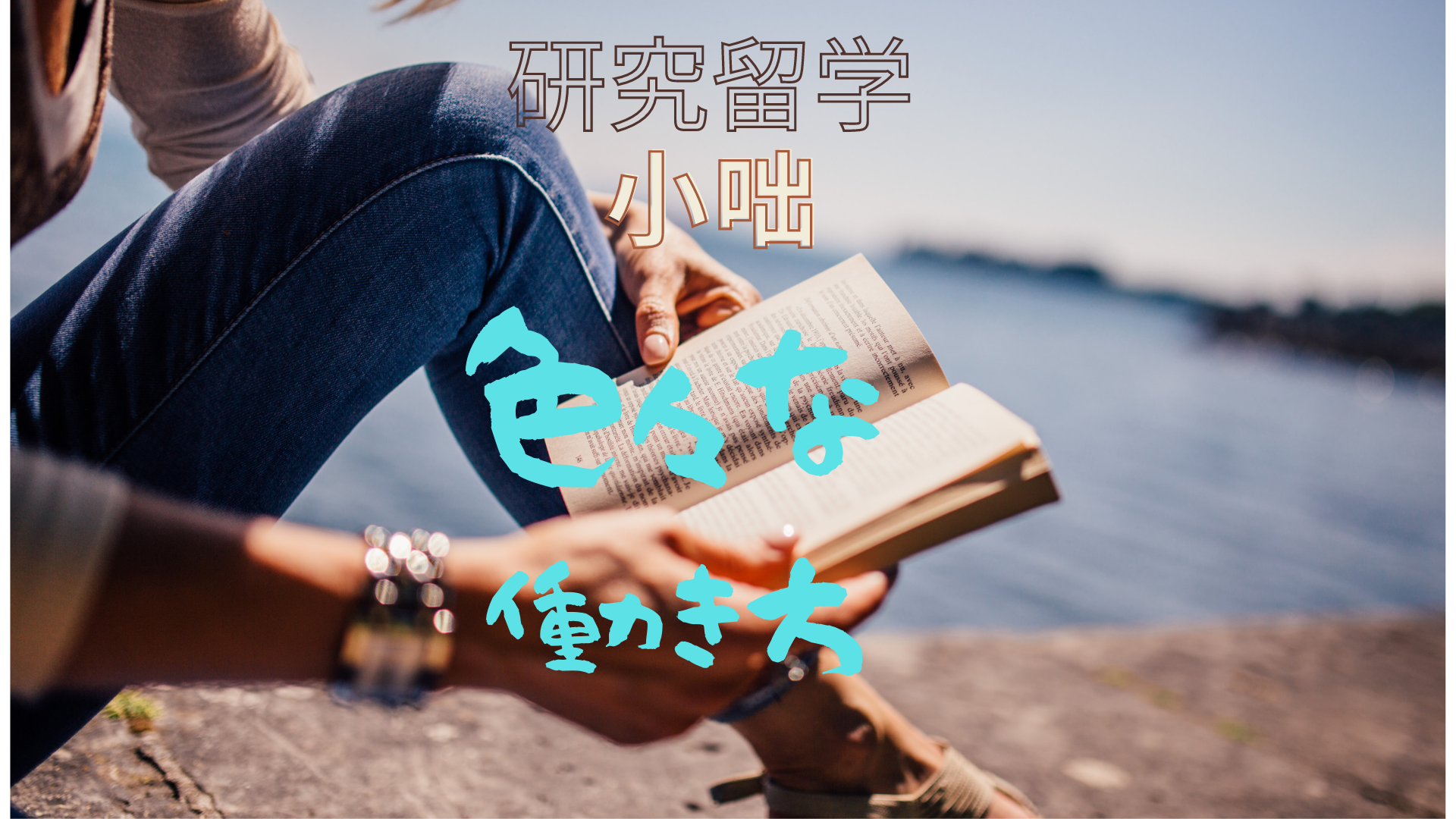
研究留学先での働き方の色々。
研究成果(データ、グラント獲得、論文)が求められるシビアな世界、
そういう中で、ポスドクたちはどのように働いているのでしょうか?
研究室やボスのスタイルにもよりますが、下記の4つのスタイルに分類されます。
1. 朝型
意外に多いのが、朝型early bardが結構います。毎朝、5時6時にきて、黙々とデスクワーク、研究している人がいます。
私は留学前の大学院生の時は、長時間型の働き方で、睡眠を削って研究したり、論文執筆したり、いつ家に帰ってるの?って生活をしていました。それが当たり前だったのです。
でも、研究留学して、朝型のヒトが、なんだかんだ時間をうまく使って、プライベートと研究を両立させている「優秀なヒト」が多い印象を受けました。
2. 定時型
朝9時から夕方5時。この時間を守ることを優先しているポスドクもいました。もちろん、「やるときはやる」ヒトが多く。基本定時だけど、一回熱が入るといつまででも研究したり、論文書いたりしているのですが、基本は定時を守るというスタイル。
私は渡米当初は日本と同じく、長時間型でしたが、徐々にこの定時型になりました。
3. 夜型
私のボスがそうだったのですが、昼ぐらいにきて、夜遅くまでというスタイル。夜遅くっていっても、せいぜい夜8時ぐらいなんですけどね。でもアメリカで夜ってホント、早くて暗くて、危険ですから、夜8時に出歩くのも怖く感じました。その中でラボに残ってデスクワークしてるんですから。
このスタイルはこのスタイルで、朝型とは違った時間コントロールをする方法のようでした。
大体午後5時過ぎて、6時ぐらいになると、ほとんどのヒトが帰路につきますから、施設全体が静かになります。その中で、集中して仕事をしたいヒトたちです。
4. 長時間型
東アジア人に多かったです。日本人、韓国人、中国人。
遅くまで、残っているのが美徳と思っているヒトが多いのでしょうね。
以上、4つのスタイルでした。
私は大学院生のときは夜遅くまで、研究室に残っているのが美徳だと勘違いしているタイプでした。今から思うと、効率は悪く、研究以外のことにダラダラ時間を使っていたのだろうと思います。
研究留学して、「研究成果」重視で、結果が出せればあとは自由で、働き方は自己責任という世界にどっぷり浸かりました。また、多くの優秀な知り合いが時間をうまく使って、プライベートと研究生活を両立させているのを見聞きするようになって、徐々に定時型(でもやる時はやるタイプ)になりました。
私の働き方は、現在、超朝型になってますが、、、
それも、研究留学して、結果を出してなんぼ、あとは自己責任じゃい精神(?)を学んだからだと思っています。
いい経験になりました。
みなさんもそういうプライスレスな経験を研究留学で積んでください。
視野が広がり、世界が広がりますよー
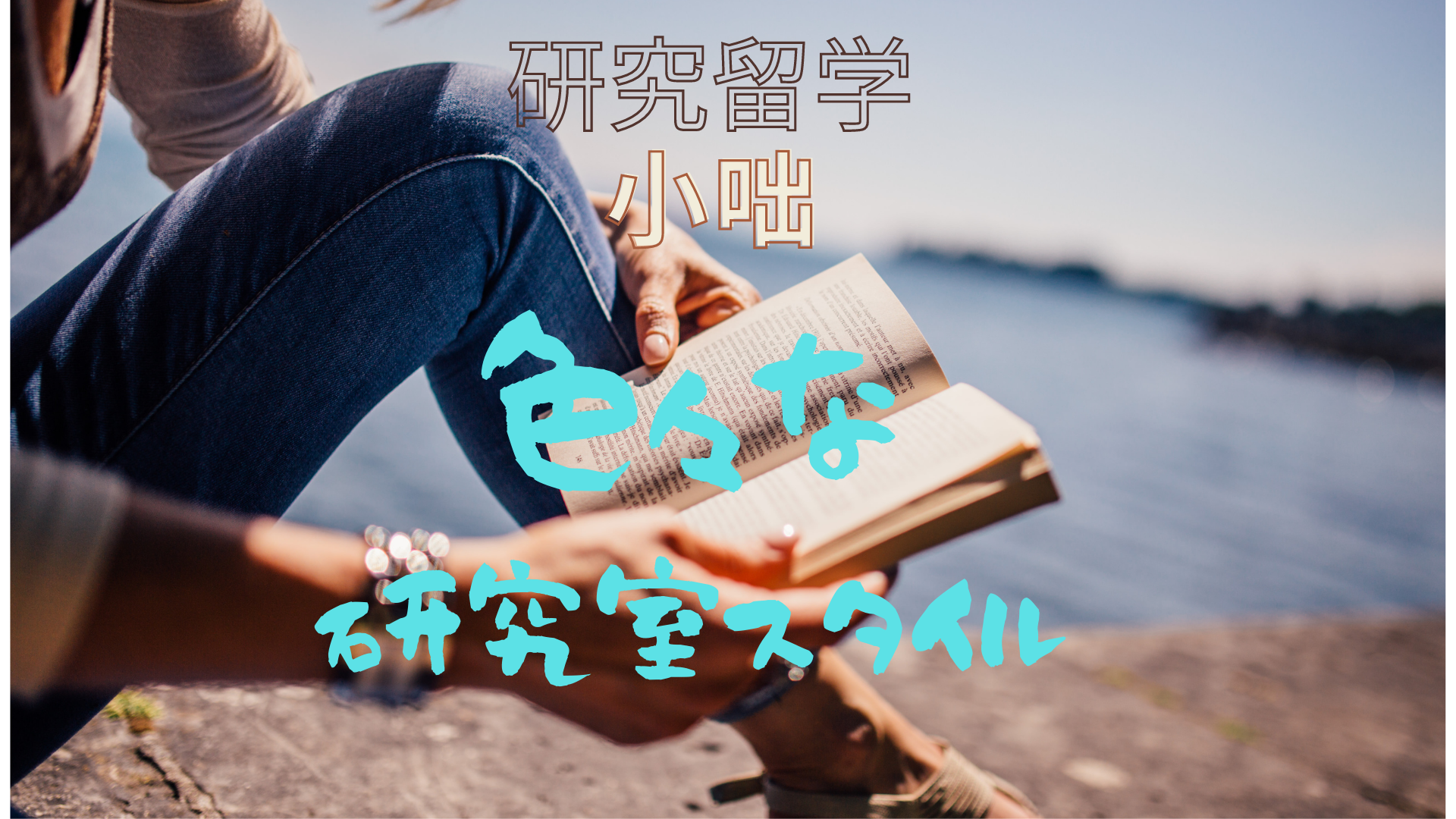
研究室のさまざまなスタイル。
私はアメリカの一地方都市、それでも有名ながんセンターでポスドクをしていましたが、
同じがんセンター内でも、さまざまな研究室のスタイルを見聞きしました。
その中で特徴的なラボのスタイルを4つ紹介したいと思います。
1. 出身国がアメリカ以外のボス
2. 同国人で固めたラボ(日本人版)
3. 同国人で固めたラボ(中国人版)
4. 夫婦主体のラボ[toc]
初めに、皆さん知っているとは思いますが、
日本の研究室のように
教授が王様のようにいて、
その下に准教授、助教が手下としている
という感じではありません。
一つの講座に何人も教授(Professor)がいます。
その中の一人が、講座を取りまとめる教授でいます。
さらに准教授(Associate Professor)、助教(Assistant Professor)が、これまた何人もいます。
日本と大きく違うのは、全員独立して、別々のテーマで別々の研究をしています。
助教だろうと、自分で獲得したグラントで、自分の裁量でポスドクを雇い、実験道具を購入し、自分のやりたいように研究を進めています。グラントがあれば、研究スペースも与えられ、バンバン研究機器も新品にできます。
その自由度は半端ないようでした。
ただグラントがなかったら、ヒトは雇えませんから、そこは講座を代表する教授の差配で、
研究費をほんの少し、割り当ててもらって、細々と一人で研究している人もいます。
そこは実力主義なのでしょう。
なかなかグラントが当たらず、研究するスペースもなく、デスクだけある「教授」もいました。
お金(グラント)を持って、結果(研究成果)を出す。
それが、全て!
あとはなんでもあり!!
「自由」ってそういうことなの?って思ったことがあります(笑)
そういう背景ですから、
ほんと、ラボの雰囲気とか、さまざまです。
1. 海外からきて、アメリカで成果を出して、ポジションを得た強者のボス(私の所属したラボ)
私のボスは、インド人でした。インドから、アメリカに来て、ポスドクとして長年研究し、そしてグラントを当てて、研究室を持ったばかり。まさに成り上がってきた人。私のボスだけではなく、多くのラボ運営者はそういう経歴を持ってました。中国人だったり、日本人だったり、ドイツ人、韓国人、もちろんアメリカ人も。
私のボスは、日本人が好きなようで、真面目に働く日本人を一人雇いたかったという理由で若く、海外に挑戦しようっていう研究者を探していたところ、何人かの候補の中から、私が選ばれたようです。
研究室のポスドクは、私を入れて2人。
ベテランポスドクの中国人。
英語の怪しい日本人(私)。
コロンビア人(女性)の大学院生。
と、ささやかな陣容でした。
それでも毎年インパクトファクターが6点ぐらいの論文を数本出していました。
2. 同国人でほとんど固めたラボ(日本人版)
日本人ボスにも色々なスタイルがあるようでしたが、私の知っている研究室の一つでは、日本人ポスドクを何人も雇っており、ほとんど日本人でした。
日本人同士のサラリーの話はタブーでしたが、お酒の席でちらっと効いた話だと、1万数千ドル/年だと聞きました。私の4分の1のサラリー?
ベテランの日本の医師を何人も、そんな安い給料で雇っていたようです。医師としてはベテランでも、研究者としては、経験不足、実績不足で、海外で安い給与でもいいから研究したいというヒトを集めていたのでしょう。
こう書くと、その日本人ボスが悪いように思われるかもしれませんが、
そこはギブアンドテイクが成り立ち、日本人ボスも、お金をやりくりして「成果」を出す「方法」として採用しているのでしょう。
個人的に、そういう方法もあるのねっ思うだけです。
他の日本人ラボでは、日本の私立大学医学の臨床系の医局と繋がりを保ち、その医局から、立ち替わり入れ代わりで、医師をポスドクとして使っていました。
使っているといったほうが良いというのは、その日本からくる医師たちは無給のようだったからです。
こういう日本人ラボで働くメリットとして、「日本語」でボスとの疎通ができる。
研究の「結果」を出すプレッシャーはほとんどなく、純粋に研究が経験できるというところでしょうね。
3.同国人でほとんど固めたラボ(中国人)
中国人ラボ、私が見聞きした中国人研究室は、ボスが中国人で、ポスドクはほとんど若い女性の中国人ポスドクで固められていました。そういう趣味?(笑)
初めその若い女性ポスドクたちをみたときは、なんとも思わなかったのですが、
一年も滞在すると、その子達がとっても可愛く見えてきたのが不思議でした(笑)
ガリガリで黒髪で、細身で、華奢で、細目で、、、今、思い出しても、それほど綺麗だったと思わないのですが、日本人、中国人からだけではなく、アメリカ人からもチヤホヤされて、モテていたようです。
一種、独特な雰囲気を持ってましたが、挨拶するようになると、ウエスタンの抗体とか、試薬を試させてってお願いしたら、優しく分けてくれたりして、話してみるといい人たちでした。
4.ボスが、配偶者をポスドクとして研究室を運営している。
いくつかの研究室で見受けられました。研究者同士で結婚して、一人はボスとして、もう一人はそのラボにポスドクとして働く。そういうスタイルの研究室が結構ありました。
このスタイルで研究室運営がうまくいっているところが多い印象です。
まあ、一人分のポスドクの給与は、そのままボス夫婦の収入になるので、研究室運営という「経営」面で、とっても良いのだろうと思います。
当たり前ですが、夫婦仲が悪いと、研究室の雰囲気も悪いですね。
以上、私が見聞きしたラボのスタイル、4つを紹介しました。
その当時は、とっても不思議に思ったりしたものです。
みなさんはどう思いますか?
それでは何かの参考になったら幸いです。
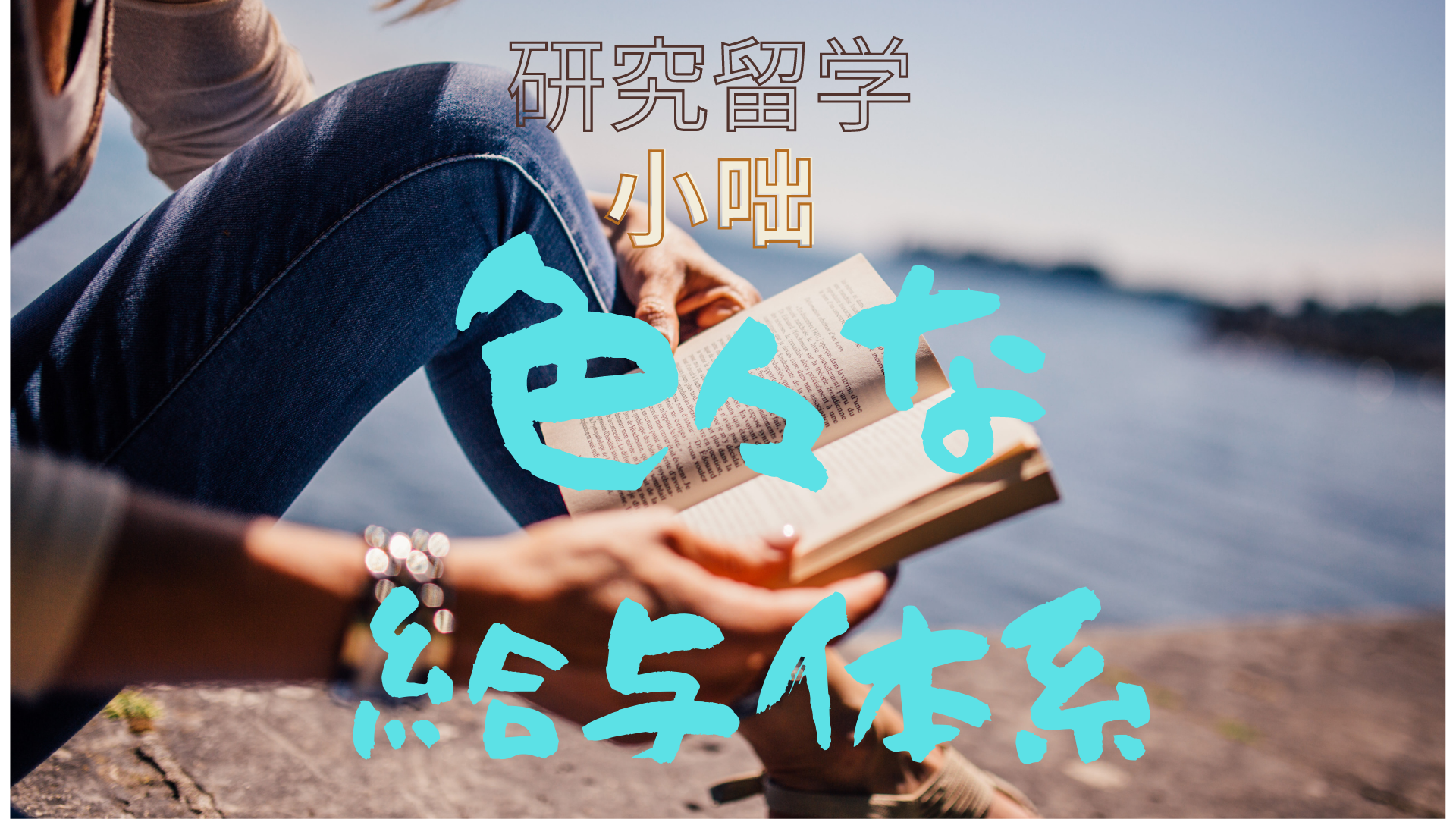
いろいろな人々。
一概に研究留学してポスドクとして海外で研究しているといっても、
いろいろな立場があります。
今回は
私が研究留学先で知り合った、そういう方々の立場や状況を書いていきます。
その中でも、給与体系での違いにフォーカスしてみます。
注: 医学系研究留学者のみの情報です。
おすすめは、2の自分でグラントを獲得する人と、4.の会社や大学からお金を出してもらうことです。
1. ボスが獲得しているグラントから給与もらって研究員として働いている人々。
サラリーは通常のポスドクの給料。多くの場合、年俸4万ドル〜、それを月々で割ってもらいます。それだけでは生活の立ち上げや、家族の養育費は補えませんので、多くの人は貯蓄を切り崩して生活します。
グラントの期間が過ぎたら、首になるかもしれません。
日本での医師免許、歯科医師免許があろうと、海外では関係ありません。
「結果」を求められます。
「結果」こそ、「正義」の実力社会。
2. 日本学術振興会から海外特別研究員として、自分でお金をとってきたヒト。もしくは上原のフェローシップなどを獲得してきた方。
学振の海外特別研究員になれれば、ボスのグラントに頼る必要がないので、かなり心に余裕があります。医師の方からすると、それでも安い給与で、家族がいると日本での生活レベルを保つのは難しいので、ある程度貯蓄を切り崩すこともあるようです。
しかしながら、ボスからのプレッシャーとか、全然違います。
私からしたら、とっても羨ましい限りでした。
3. お情け程度のサラリー。ほとんど自分の貯蓄を切り崩して生活している方。
医師の方で、こういう方が結構いました。
その中でも、いろいろ立場が違うようで、普通に研究を頑張りたいからってこられて、慎ましい生活をしながら、頑張っている人もいれば。
私立大学医学部の医局の関係で、海外で「雑用」するのが、その医局のルールだそうで。毎年、入れ替わり立ち替わり、同一の研究室に来ているヒトもいました。こういう方々は、研究もやることが決まっていて、別に結果が出なくても、結果(論文)が出たときに多くの著者の中に名前を入れてもらえるというメリットがあり。他のポスドクが喘ぐプレッシャーとは無縁の世界で、「留学」を満喫されている方々もいました。
話を聞くと、研究しにきたの?バカンスにきたの?って、真面目に研究しにきた人からすると理解不能な人たちではありますが。
正直、羨ましくもありました(笑)
4. 会社、もしくは大学から給与をもらっている人。
一部の医学系私立大学では、研究留学するのに、給与を払ってくれるところもあるようです。特別手当扱いのようで、日本での給与よりも良いのだとか。
また、製薬会社系の研究員の方とかも、会社でお金を払ってもらってる方もいました。
こういった方々の多くは真面目で、真剣に研究に取り組まれている方が多く。
ボスからしたら、給与を払わなくてもよい、真面目な働き手なので、大事にされます。
とっても羨ましかったです。

実際に研究留学の準備をしましょう。
(注意:家族の理解を得た上でのことです)
[/st-mybox]
これを一番最初に行う、最初の一歩です。
「したい」ではダメです。「します」宣言です。
周りのヒト、医局の先輩、後輩、上司すべてのヒトに伝えましょう。
教授に、なかなか言えないと思う方もいるとは思いますが、
そこは個別で面談の機会を作ってもらうか、最悪、メールでも構いません。
その上で、よかったら推薦文を書いてもらえないかお願いしてみましょう。
私は自分で自分の推薦文を書いて、よかったら添削してください〜ってお願いしました(笑)。
その当時の医局の教授とは、もちろん精神的な大きな壁がありましたが、
思い切って、自分で書いた自分の推薦文を渡したら、「おお〜。わかった!!」
って驚いた様子でしたが、快諾してくれましたよ。
宣言して、動き出して、初めて周りは、「コイツ本気なんだっ」て思う様になります。
今まで、散々、研究留学したい!!ってことあるごとに言っていても、、、
結局、ヒトはヒト、自分の事を気にしていませんからね。
2.研究留学先を探す。
研究留学先の探し方は色々あります。
3.研究助成金を申請する。(2,と同時進行で行う)
「生命医学をハックする」https://biomedicalhacks.com/2019-10-27/fellowships/
という、ブログが非常に参考になると思います。
研究留学のデメリットの「おかね」の問題を削除、軽減するために、そして、研究留学を成功に導くために研究留学助成金を申請しましょう。
最初に書いておきますが、
研究留学助成金がもらえないと、研究留学できないってわけではありませんから〜(笑)
研究留学先を探す際に、コネクションがない場合、
大事なポイントとして、2.の研究留学先を探すと同時進行でしましょう。
研究助成金を申請する際に、受け入れ先の承諾がないと申請できないものが多いです。
ですので、手順として,
多くの海外の研究室は自前のグラントで、人を雇ってます。なので、英語の怪しい、会ったこともない日本人に給料を払うって、かなりリスクだと考えるヒトが多いです。
しかしながら、チャレンジするヒトに寛容なボス(研究室運営者)が多いので、
日本で助成金申請して、お金を持ってくるんだったら受け入れても良いかな?と
思う人もいます。
また、研究分野が似通って、申請内容が面白かったら、助成金が当たらなくても、一回電話で話そうか?とか一回、どっかの学会で会ってみようかな?って興味を持ってくれるでしょう。
コネクションがなければ、こうやって、自分で留学先を探すのが、良いでしょう。
ではGood Luck!!

研究留学を成功させるためには
以上3点が大事だと思います。
1つ1つ説明していきます。
1.目的をはっきりさせる
一言で「研究留学」と言っても、様々な形があります。
スケール大きい人では、日本に帰る気はなく、アメリカでラボを持って、研究するんだ!!って方もいらっしゃいますし、
ちょっと数ヶ月、「研究留学」という滞在をしてみたいって方もいます。
ここでは、数年、研究し、なんらかの実績を残し日本に帰国することを目的としている方に向けてですが、
みなさん、なんとなく「目的」を持っていますよね?
それを「はっきり」させたおいた方がいいです。
私は「はっきり」させていなかったため、研究留学から日本に帰国後10年ちかく経って
やっとあの時の「苦い経験」を「いい思い出」に昇華出来つつあります。
それでも完全な良い思い出になってませんけど、、、
客観的に私の研究留学を振り返ると
たった2年の研究留学で、
なんのつてもない研究留学先でサラリーをもらいながら
インパクトファクターが9点ぐらいの雑誌の筆頭著者で論文を出して
帰国後、その論文が受理されました。
しかも縁もつてもない、日本の研究職にあり付けました。
友人は研究留学は「大成功」だと、言ってくれます。
でも、今でも心に蟠りがあるのは、
研究留学前に私が、研究留学も目的を「はっきり」させていなかったからだと思います。
研究留学先では、予測できないことが多分に生じます。
その時に、自分の研究留学の目的はなんだったのか、振り返って、
そして割り切って、次の手を考えることが大事だと思います。
ですから、しっかり目的をはっきりさせて、
出来たら、何かに書いておきましょう。
いつでも振り返れるように.
2.デメリットを削除もしくは軽減する準備をする
研究留学のデメリットとして
金銭、家族、帰国後のポジションをあげました。
金銭については、単純に貯蓄をしましょう。
そして、研究留学助成金を申請し、獲得しましょう。
家族については、
配偶者がいるなら、まずは配偶者に「理解」してもらうことが大事です。
私は妻と幼い子供がいましたから、
奥さんには、ことあるごとに「研究留学」への想いを語ってました。
そして、奥さんの不安をなくすため、
自分の研究留学するために、どういう準備が必要で、
なぜ必要なのか、
家族のことはどうするのか
帰国後、どういうことが予想され、
研究留学がうまく行っても行かなくても、こうやって家族を養うとか
様々なことを、想定し
「夢」ではなく、家族の「スケジュール」を書き出し
奥さんに何度も相談、、、
というかプレゼンしました(笑)
そういう過程は、自分の目的意識をはっきりさせ、
前に進むために大事だったと思います。
研究留学中も、
必ず週末は私が子供を連れ出し、奥さんに一人の時間、ゆっくりできる時間を過ごしてもらえるように心がけました。
私は心がけてはいましたが、奥さんからしたら、それでも「十分」ではなかったとは思いますが、、
まあ、今でも仲良く出来ているのは、その時の経験があったからではないかなっと思います。
この「家族を大事にしなさい」「配偶者を大事にしなさい」
は私の大学院での研究を指導してくださった先生(人生の恩師だと、思ってます)の研究留学におけるアドバイスでした
このアドバイスを私は大事にしていましたし、
結果、それがよかったなと、しみじみ思います。
3.留学先では、新しいことに挑戦する
恩師のアドバイスとして、
研究留学先では、ヒトの嫌がることも、率先してやりなさい
アメリカでは、君は英語の拙いただの外国人なんだから、
新しいことに積極的に挑戦し
日本での業績、経験を鼻にかけるようなことは慎め
「ばかにしているのか?」って思うようなことがあっても、
「結果」を出して、見返すようにしなさい。
と切々と教えてもらいました。
私はそのアドバイスを胸に刻み、
研究留学先で心掛けていました。
みなさん、研究留学を志すからには、大なり小なり、プライドがあると思います。
私もありました。
でも、留学先では、初めはただの英語の拙い外国人です。
拙い言葉で、汚い言葉で言い返すのではなく、
「結果」を見せれば、自ずと周りの貴方への扱いは変わってきます。
それまで、頑張りましょう。
また、新しいこと、方法に積極的に挑戦しましょう。
研究の進め方、考え方も「自分の日本でのやり方」に拘らず、
留学先のやり方を受け入れ、やってみましょう。
これが、案外、出来ない人が多いのかもしれないなって思います。
以上3点、
当たり前のことばかりですけど、
研究留学をより良いものにする大事な、基盤となる「ヒント」だと思います。
ぜひ参考にしてみてください。

私は2009年から2011年の2年間、研究留学をしていました。
30代前半の頃でした。
もう、日本へ帰国後、10年以上たち
その頃、ブログを日記がわりに書いてwebに公開していたものも
帰国後削除したので、web上に何も残っていません。
現在では、日本で研究者として生計がなんとか成り立っているので、
私の研究留学は「成功」だったのでしょう。
その頃はただただ、ガムシャラに、研究留学に、研究に、研究で生きていくために突き進んでおり、ブログも愚痴ばかりの「愚痴ブログ」だった様に思いますが、
今なら、後進の有望な若い研究者を志す人たちに、客観的なアドバイスができるのではないかと、この記事を書こうと思いました。

以上、多くの人に当てはまるであろう
メリット、デメリットを書いてみました。
これらは、私の10年以上前の経験からですが、
10年経っても、スマートフォンが発達しても、
ほとんど普遍的なものです。
また、COVID-19のコロナ禍で、国際交流は断絶していますが、
だからこそ、今後より、国際交流経験の有無が貴重になってきます。
むしろ、チャンスです。
ぜひ、若手の研究者は研究留学を目指しましょう!!