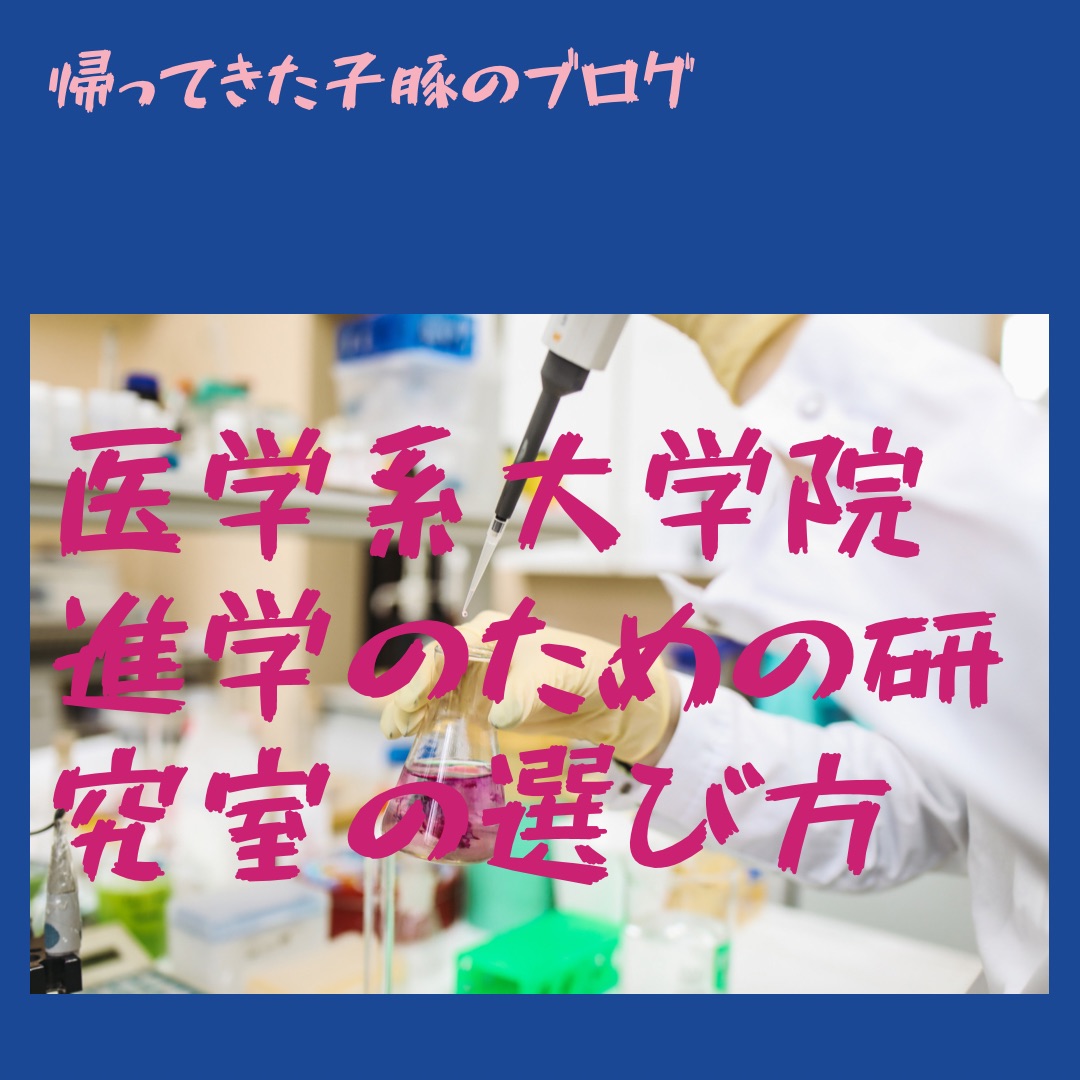医師、歯科医師が博士課程に進学する際に研究室を選ぶ際のポイントと注意点を挙げていきたいと思います。
理学系の方は、修士課程とか博士課程への進学は学部生の頃から、一つの選択肢として身近なことですので、よくわかっている方が多いとは思いますが、
医師、歯科医師の方は、大学院進学の研究室を選ぶ時に、どういう落とし穴があり、どういう基準で研究室を選べばいいか、よくわかっていないと思います。そのため、の基準とあるものを私の経験からお知らせしたく思います。
大学院進学の時の研究室の選び方
- 自分の興味のあることを研究テーマにしている
- 研究業績をよく調べる
- 研究業績のimpact factorを調べる
- 筆頭著者と責任著者が誰が、どの立場で行なっているのかを調べる
- 研究室の誰が責任著者で、教員それぞれの、ここ5年の獲得業績を調べる
- 外部資金獲得状況を調べる
- 研究室の教員、大学院生の移動状況を調べる
- 自分の興味のあることを研究テーマにしている
当たり前のことですが、自分の興味のあることをやっている研究室を選びましょう。
当たり前ですが、大事です。何より、大学院に行くメリット、デメリットをよく考え、その研究テーマは自分の貴重な4年の年月とそれに伴う、学費、臨床経験を積む時間を割くのですから、何度も自問自答しましょう。
- 研究業績を調べる
- 研究業績のimpact factorを調べる
自分の興味のある研究テーマを行なっている研究室が見つかっても、注意しなければいけないのは、しっかり研究業績を出しているのか?が大事です。
まずは指標として、研究論文のimpact factorを調べましょう。大体どの程度のレベルの雑誌に、研究論文を発表しているのか?1年で何本?impact factorは一年トータルどのくらい、その研究室からでているのか?
地方国立大学医学系大学院でしたら、まあ、impact factor 5点レベルを年に一本出せていれば、まずまずです。1年で獲得しているimpact factorが3点以下でしたら、基礎系、臨床系の研究室に関わらず、ちょっとレベルが低い研究室と言っても過言ではないと思います。
- 筆頭著者と責任著者が誰が、どの立場で行なっているのかを調べる
研究室から出ている論文でも、著者名をよくみましょう。誰が、どの立場の人が著者名の何番目に並んでいますか?また責任著者(corresponding author)は誰になっているのか?
例えば、ある研究室の研究業績が昨年3本ありました。Impact factorは平均5点でトータルで15点でした。それだけでしたら、そこの研究室はそこそこのレベルだと思われるでしょう。しかし、その3本の責任著者を確認し、その研究室のメンバーがどの順番で、どこにあるのかみてみると、案外実情が違っていたりします。例えですが3本中2本は教授だけ名前が載っているが、他の研究室のメンバーの名前はない。その研究論文の責任著者名は他の大学の他の研究室のヒトで、研究テーマも研究室のテーマと全く関係なく、その教授の名前も著者名の中で、真ん中あたり、、、その2本の研究論文でimpact factor14点で、残り1点の研究論文は、その研究室の大学院生が筆頭著者で、教授は1番最後、責任著者は准教授で二番目に名前がある、、、
結構、こういうことがあったりします。その場合、その研究室の研究業績は1本だけの1点と考えた方がいいでしょう。しかも、その研究室から出ている論文の責任著者が教授でない場合、研究内容、研究テーマがその研究室のテーマではなく、准教授の研究テーマかもしれません。そうすると、その研究室を主催する教授の研究テーマでは一本も論文が出ていないことになります。しかも、准教授の研究論文の最終著者(ラストオーサー)に当たり前に載ってる、、、今の時代、主任教授であろうと、研究室の研究費を多少その研究に充てていようと、研究に関与せず、研究指導していない場合はラストオーサーになるべきではないのに、、、。
このことから、推測できるのは、この研究室の教授は、価値観、研究倫理観が20年前以上で止まっているトンデモ教授かもしれません。しかも、外部の研究論文に教授の名前だけ、、、自分の研究室の教員、大学院生の指導せず、自分だけ業績をカサ増ししているクズかもしれないと考えることができます。
- 研究室の誰が責任著者で、教員それぞれの、ここ5年の獲得業績を調べる
過去一年分の研究業績だけではなく、できたら、5年ぐらい前まで、遡って調べてみましょう。
研究室の誰が責任著者で、その研究論文のテーマは誰のものか?、筆頭著者はどういう立場の人か?5年遡って調べれば、よりその研究室の特徴が見えてくるでしょう。
先ほどあげたような例が5年遡っても、同じような傾向でしたら、間違いなくブラック研究室でしょう。
- 外部研究資金の獲得状況を調べましょう
研究は研究費がなければできません。科研費もしくは外部から研究費を獲得しているのか、しっかり調べておきましょう。そして、その研究費は誰が獲得しているのか?もしっかり調べておきましょう。
例えば、先ほどの仮想研究室の外部資金の獲得状況を調べてみたら、科研費を教授が獲得していました。共同研究研究者として、教室員全員の名前が載っています、、、おう!すごいですね!
優秀な教授なのかな?
研究テーマを見てみたら、准教授の研究テーマでした、、、
さてこれはどう考えればいいのでしょう?
この場合、准教授がゴーストライトして教授の名前で科研費を獲得している可能性が高いです。
そういうことを教授がさせている。つまりはパワハラ体質のクズ教授の可能性が高いかもしれません。
このように、研究業績を調べれば、気づくことが多いので、しっかり調べましょう。
3. 研究室の教員、大学院生の移動状況を調べる
さて、次にその研究室、もしくは大学院生の移動状況を調べておきましょう。
30代−40代の研究室のメンバーが、5年以内に、2名以上移動していたら、ブラック研究室の可能性が高いです。ただ、ごく稀に超絶ホワイト研究室でも、5年以内に数名移動していることがあります。まあ、ホワイト研究室の場合は、移動した人たちは皆、出世もしくはキャリアアップしていますから、移動先も調べておくといいでしょう。
そうではなかった場合、助教から助教で移動していたり、
国立大から私立大学に、もしくは
有名私立大学から下流私立大学にポジションの位がそのままで移動していたら、まず間違いなく、その研究室から逃げていると考えていいでしょう。
以上4点、大学院進学のための研究室の選び方でした。
これが何かの参考になればいいと思います。
個人談
今の時代いないとは思いますが、研究室を選ぶに際し、「先輩に勧められた」とか、何かを餌に、例えば、ポジションを餌に「この研究室にいけ」と教授に指示されたとか、、、、が主な理由で、大学院に進学する場合、そういう方を否定するつもりはありませんが、アドバイスとして、4年の年月、その間に詰める臨床経験とか、稼げるお金、支払わなければいけない学費とかをよくよく考慮して、「自分の人生の進むべき道」を自分の責任でしっかり考えた方がいいと思います。
個人談ですが、私は、その当時の教授に専門医になりたければ、大学院行って博士号取ってないと、専門医にさせないと言われたのが、大学院に進学したのが大きな動機でした、、、
私は運良く、良い指導者に恵まれましたが、あくまで「運」が良かっただけ、、、
今回の内容は過去の自分に、自分の失敗からアドバイスするつもりで書いてみました。
もし、医学系大学院に進学を考えていらっしゃる方へ、何かの参考になれば嬉しいです